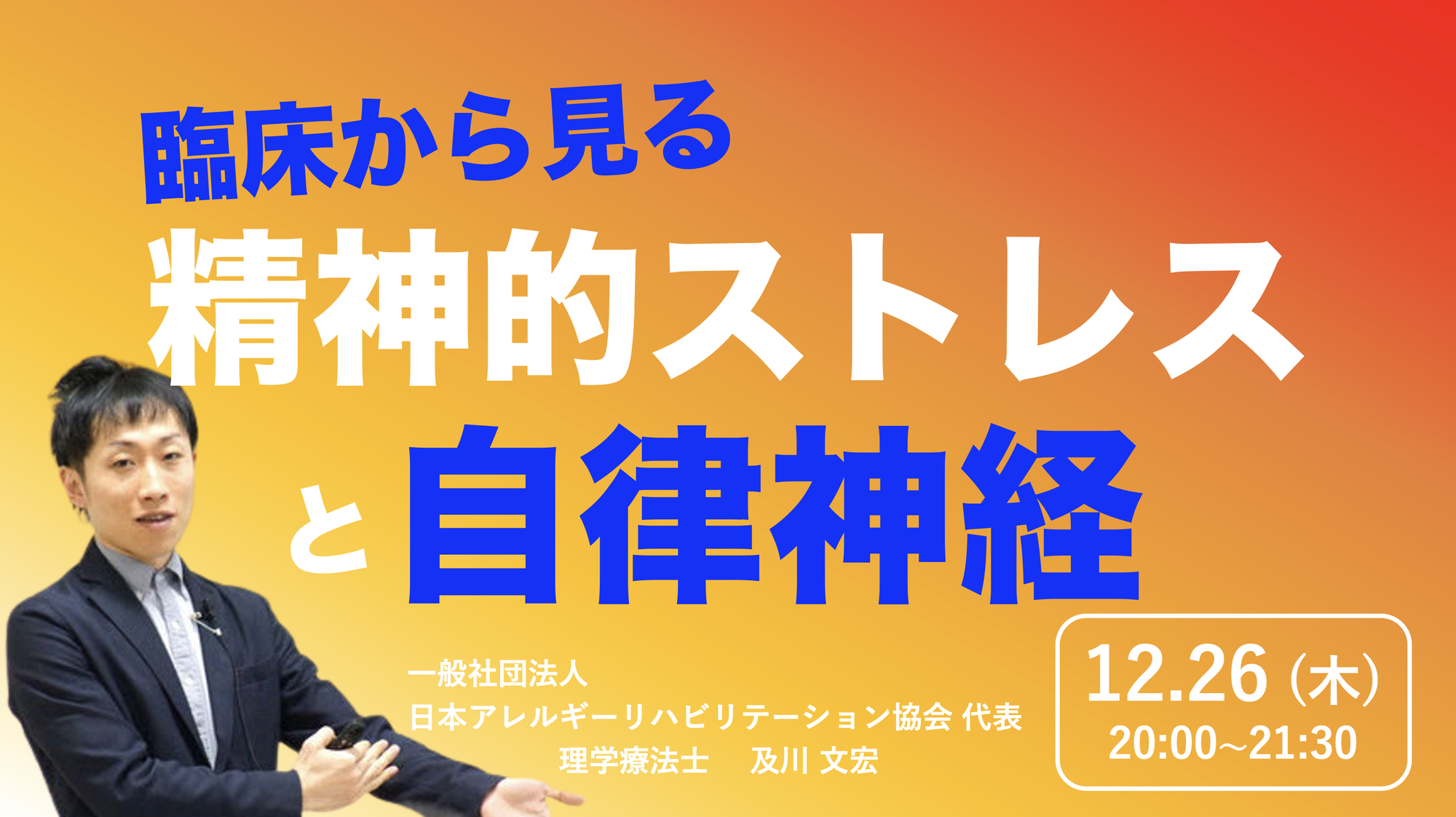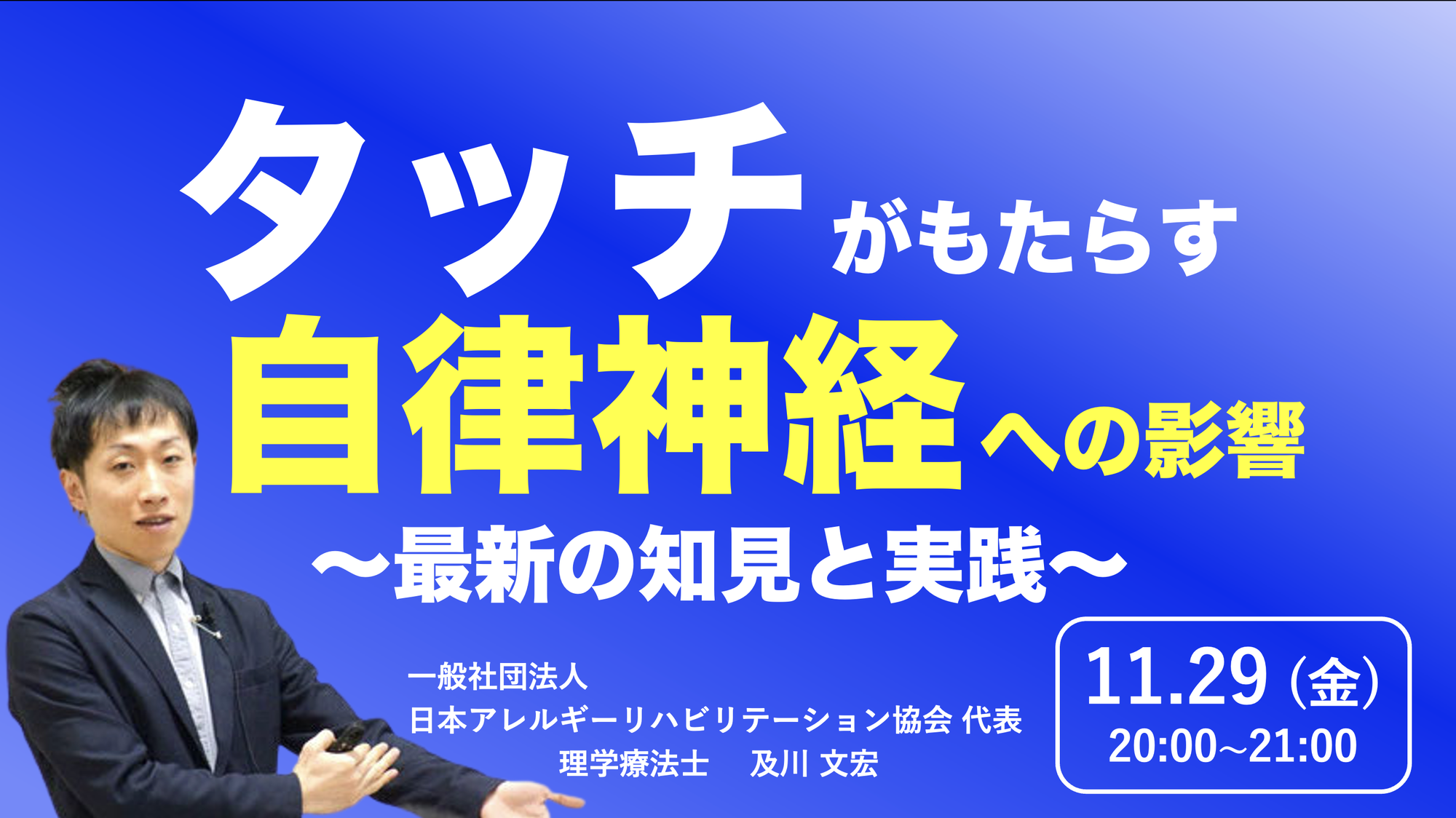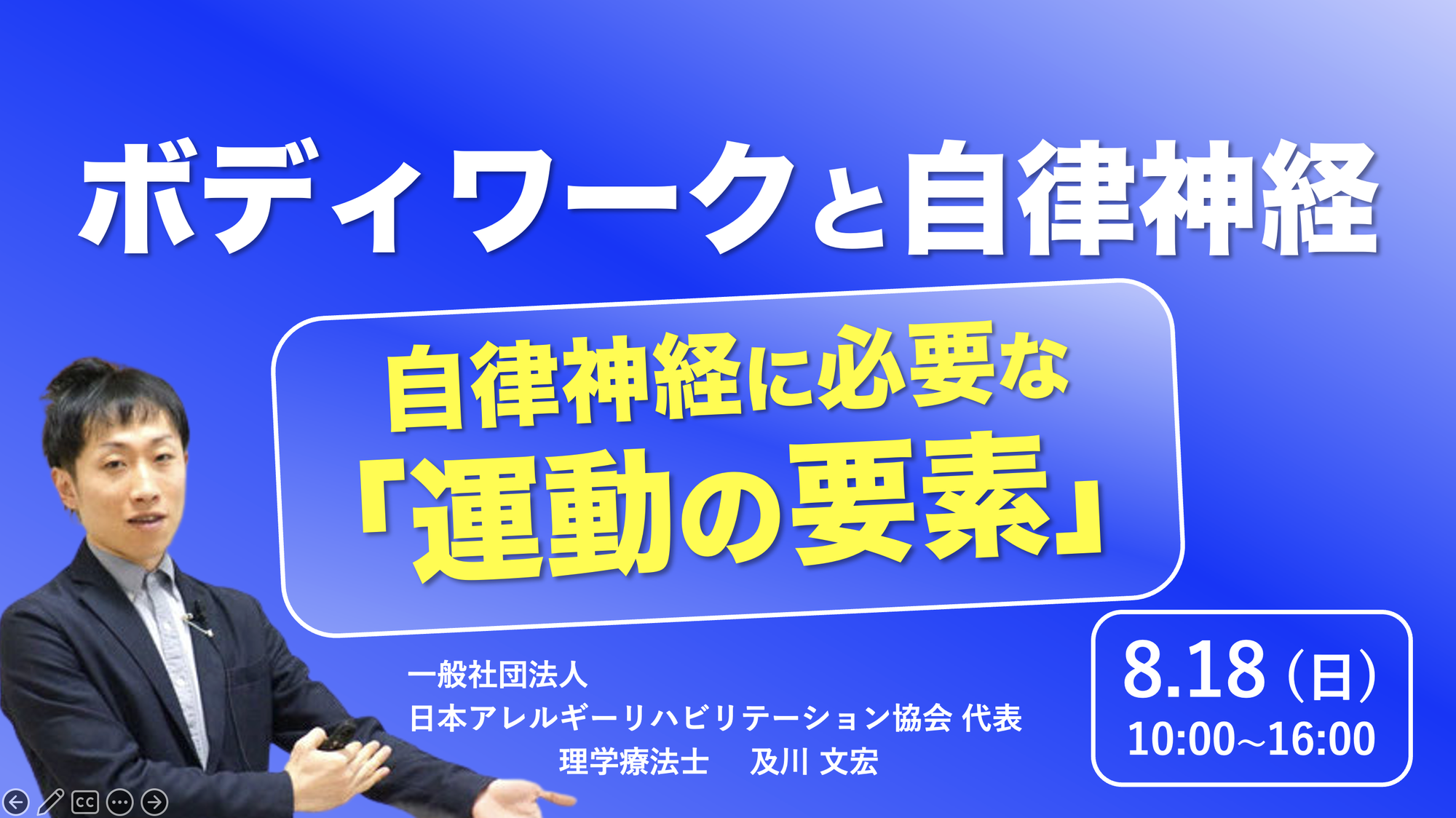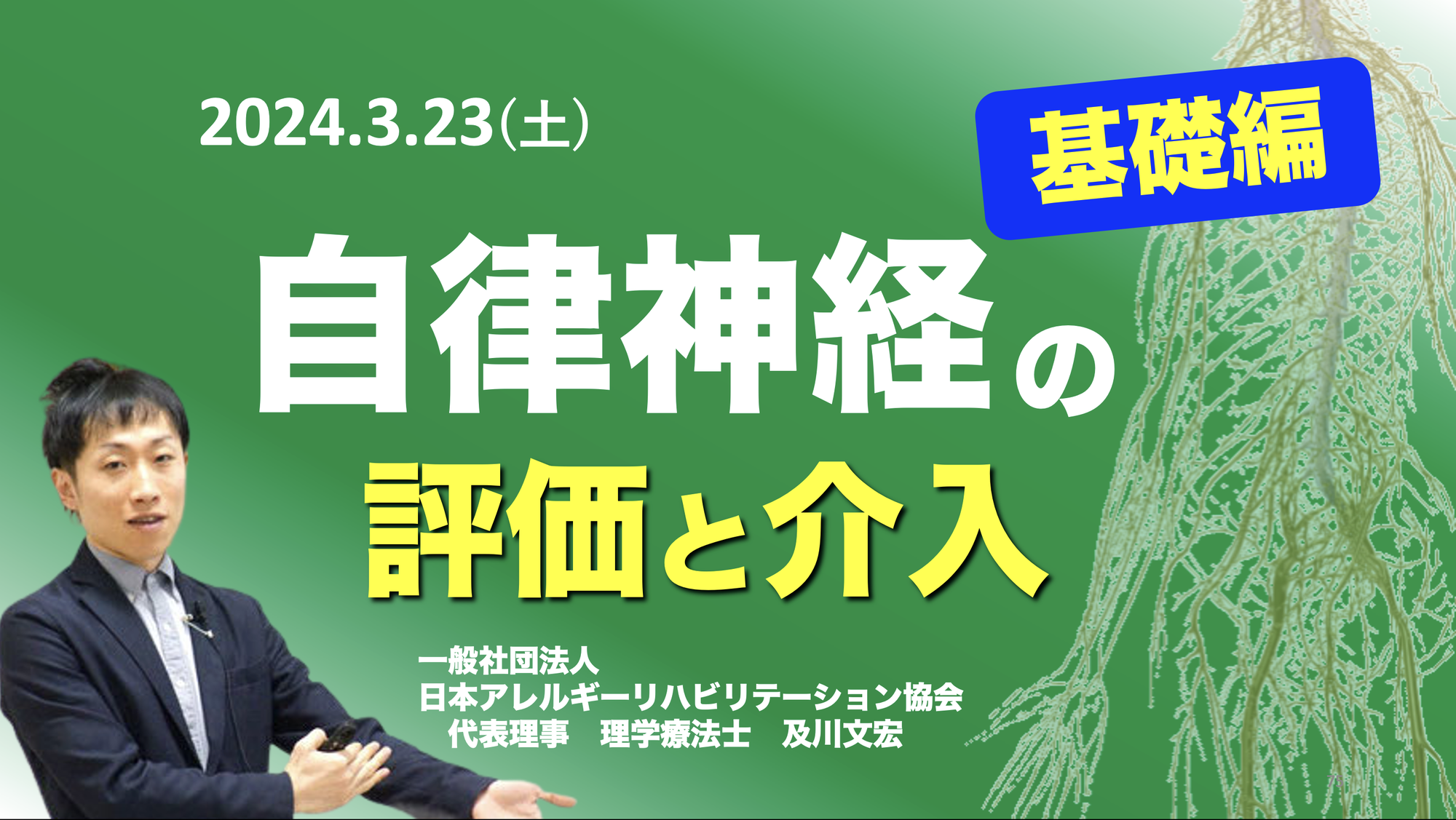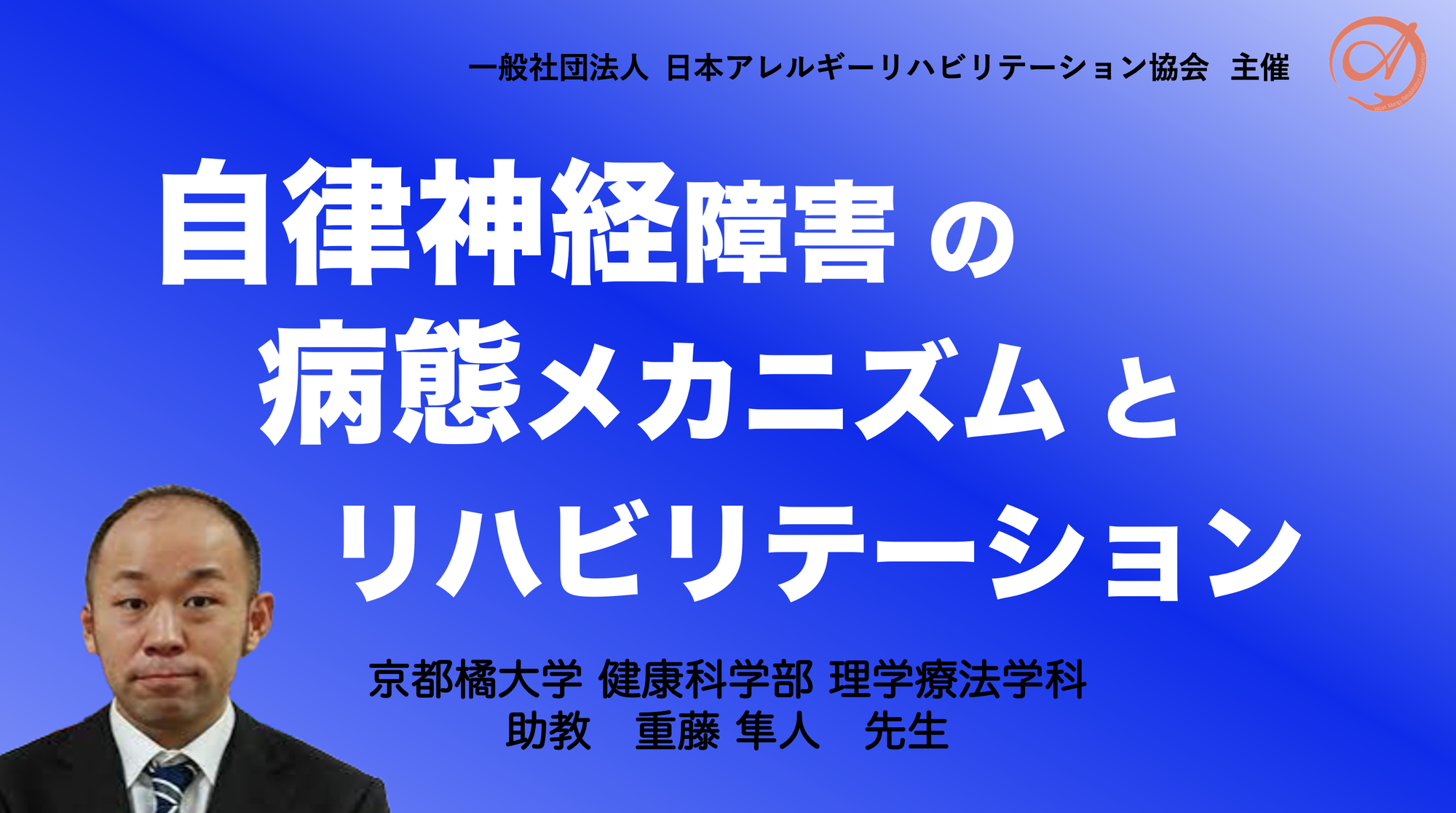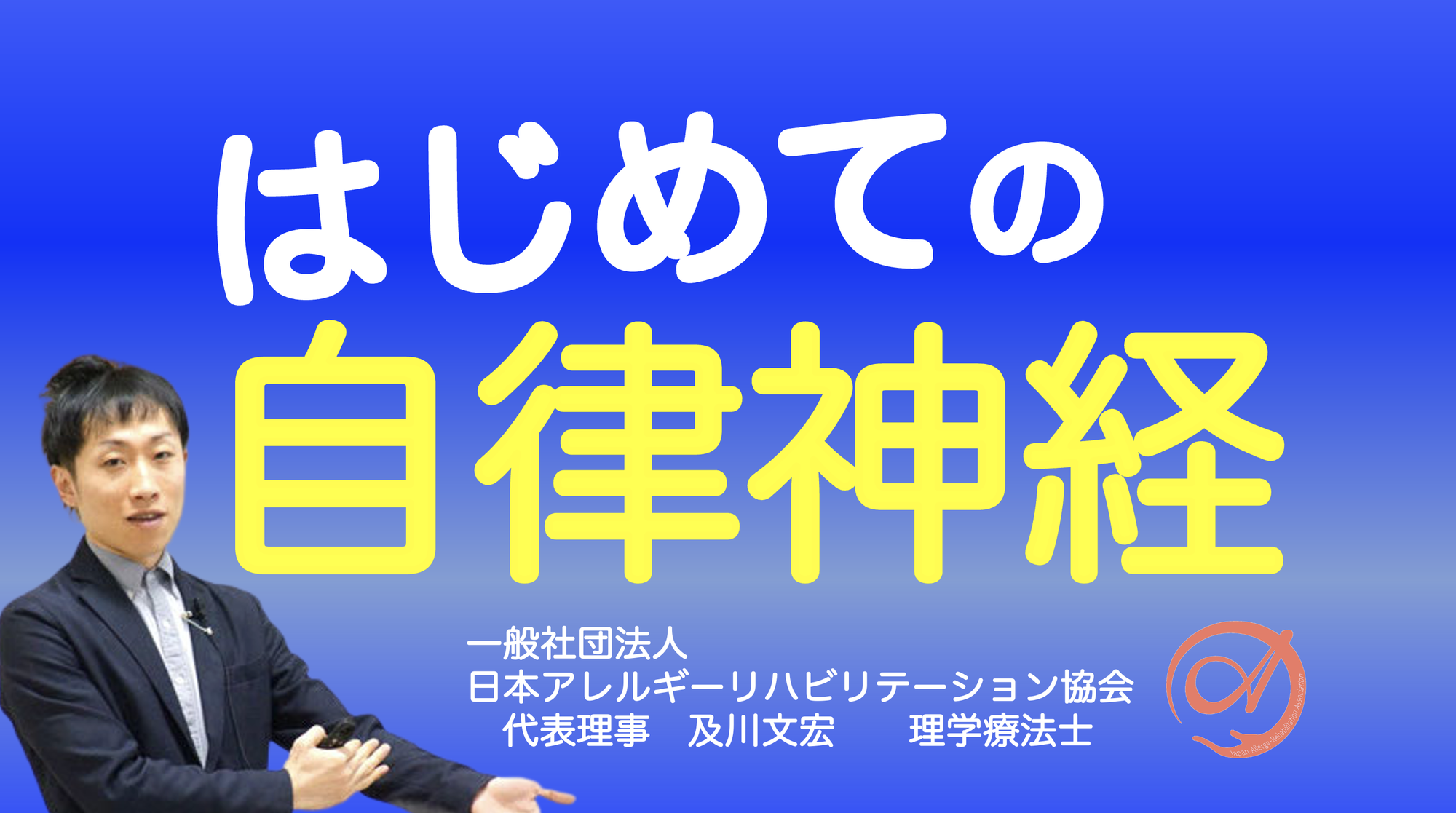自律神経
『自律神経の乱れに気づく問診の仕方』
日時:1月29日(水) 20:00~21:30
会場:zoom
視聴期間:2025年2月1日~2025年2月21日
講師 理学療法士 及川文宏
『臨床から見る精神的ストレスと自律神経』
日時:12月26日(木) 20:00~21:30
会場:zoom
視聴期間:2024年12月29日~2025年1月15日
内容
・精神的ストレスと自律神経
・運動と精神的ストレスの自律神経反応の違い
・ストレスから身を守るには逃げるが勝ち
・脂肪肝とストレス、脂肪肝の役割
・ストレスを知るための問診
・ストレスのモニタリング
・「考え癖」が自律神経を乱す
・ストレスの対処法(コーピングなど)
・自律神経が乱れやすい人の性格
講師 理学療法士 及川文宏
『タッチがもたらす自律神経への影響』
〜最新の知見と実践〜
日時:2024年11月29日(金)20:00-21:00
場所:zoom(リアルタイム参加/動画視聴)
視聴期間:12月1日〜12月15日までの配信
講師 理学療法士 及川文宏
対象:どなたでも参加可能
内容:
・タッチ (触れることやセラピー) と自律神経の繋がりについて
・上記についての最近の論文の紹介
・自律神経の乱れを持つ方に対する触れ方の注意点
・今年の自律神経学会で発表した研究について
『自律神経を整えるライフスタイルの実践』
日時 9月8日(日) 10:00〜16:30
会場 神奈川県
各タイトル・講師
『自律神経を整えるために必要な身体の使い方』理学療法士 及川 文宏
『トレーニング種目から組み立てる自律神経アプローチ』理学療法士 石井 りえ
『自律神経と体内水と入浴』理学療法士 後藤 和樹
『自律神経を整えるヨガ的生活』作業療法士 高橋 志帆
『山登り理学療法士が伝える、歩行と自律神経』理学療法士 寺島 佑
『自律神経を整えるための睡眠の知識』理学療法士 本塚 貴裕
『自律神経とボディワークのつながり』
〜ボディワークに求める運動の要素〜
日時 8月18日 (日) 10:00〜16:00 (当日現地参加/アーカイブ配信あり)
※アーカイブ動画配信:8月21日~9月15日
会場 東京都内(当日現地参加者にお伝えいたします)
対象 ボディーワークに興味のある方であれば、どなたでも参加可能
講師 理学療法士 及川文宏
一般社団法人日本アレルギーリハビリテーション協会
内容
・交感神経、副交感神経ために必要なそれぞれ動きの要素
・胸郭と骨盤の動きと分離と協調
・抗重力筋活動の持久性と自律神経
・最適な負荷量の設定の重要性
・自律神経の負荷と休息
・運動中の呼吸の意識と注意点
・筋緊張のコントロール方法
・脱力の重要性
『自律神経の評価と介入の基礎』
〜リハビリテーションにどう活用するか?〜
日時
オンライン 5月22日(水) 20:00〜21:30
対面実技 6月 9日(土) 14:00〜19:00
会場 南魚沼市広域働く婦人の家 2F軽運動室きに影響を与えるもの
『自律神経の評価と介入(基礎編)』
日時 3月23日(土) 10:30〜16:30
場所 東京都内
講師 理学療法士 及川文宏 一般社団法人日本アレルギーリハビリテーション協会
内容
•自律神経に問題ある人の身体的特徴
•自律神経の数値化
•自律神経のバランスの表現
•交感神経が亢進する3つの原因
•ストレスと自律神経
•自律神経障害と身体的問題の生理学的つながり
•自律神経の働きに影響を与えるもの
『自律神経障害の病態メカニズムとリハビリテーション』
日時 3月13日 (水) 20:00~21:30
場所 ZOOM
講師 京都橘大学 健康科学部 理学療法学科 助教 重藤 隼人 先生
参加費 3,000円
※アーカイブ配信あり
当日収録した講義内容の動画を3月15日~3月31日の期間で限定公開します。
『今日からはじめる自律神経』
日時 9月17日(月) 12:00〜16:00
会場 東京都江東区
(現地参加申込者には申込後に詳細をお伝えいたします)
講師・内容
『自律神経を整える』
〜解剖・生理・運動学の視点より〜
理学療法士 佐藤 慶太
『ストレスと脳科学』
〜瞑想が自律神経を整えるメカニズム〜
理学療法士 寺島 佑
『ツールを使ったセルフケア』
〜メディカルアロマで考える自律神経ケア〜
理学療法士 石井 りえ
『自律神経と食事管理のポイント』
管理栄養士 和田 宵湖
『自律神経の不調とは?』
〜自律神経の9つの分類方法〜
理学療法士 及川 文宏